現在、世界中で普及が進んでいるEV。
ガソリン車に加えて電気自動車も出てきて、「選択肢が増えた」という点では歓迎したいところですが、最近のEV推しにはどうも裏側を感じてしまいますよね。
というわけで、なぜ世界的にEVが推されているかの理由についてまとめました。
EVが推される本当の理由
現代社会におけるEVの推進は、地球温暖化への対応、化石燃料依存の脱却、CO2排出量の削減、そして経済や産業構造の転換など、複数の要因が絡み合って進められています。
とりわけ、EVは「環境に優しいモビリティ」としてのイメージが強く、国際的な政策や規制、そして自動車メーカーの戦略によって後押しされています。
加えて、ガソリン車は非常に多くの部品を使うため、それらを組み合わせる技術などはトヨタなどの既存の企業に勝つことはできません。
一方でEVであれば新興企業でも勝負ができるため、そういった点からもEVが持ち上げられています。
EVの意外な歴史
- 電気自動車は1881年に発明され、ガソリン車(1886年)よりも早かった
- 1900年頃は、電気・ガソリン・蒸気が三つ巴で争っていた
- ガソリン車が「給油が早く」「航続距離が長い」などの理由で普及
- EVは何度もブームと失速を繰り返してきた
実は電気自動車は、ガソリン車よりも古い歴史を持ちます。1881年にフランスのトルベによって発明され、1886年にカール・ベンツがガソリン車を発明しました。
1900年前後には、内燃機関車・蒸気自動車・電気自動車の三者がしのぎを削っていましたが、T型フォードの大量生産とともに、セルモーターやマフラーの実用化が進み、ガソリン車が急速に普及することとなりました。
その後も戦時中のガソリン統制や、大気汚染への懸念、国際会議での温室効果ガス規制などの影響で、EVは何度も脚光を浴びる場面がありましたが、持続的な普及には至っていませんでした。
技術革新の要所
EVが再び注目を浴び、実用性を持つようになった最大の要因は、バッテリー技術の進化にあります。
初期のEVに使われていた鉛蓄電池は重く、航続距離も短いため実用には不向きでした。
そこに登場したのが、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池です。特に1991年にソニーがリチウムイオン電池の量産化を実現したことで、軽量で高エネルギー密度な電池の搭載が可能になり、EVの航続距離も飛躍的に向上しました。
この進展により、三菱自動車の「i-MiEV」や日産の「リーフ」といった市販車が登場し、EVは本格的な市民権を得るに至ります。
| 時代 | 主な動き |
|---|---|
| 1990年代 | カリフォルニアZEV規制、GMのEV1登場 |
| 2000年代 | リチウムイオン電池普及、三菱「i-MiEV」、日産「リーフ」登場 |
| 2010年代 | 世界的なCO2規制強化、パリ協定 |
国別のEV推進の事情
| 国・地域 | EVシェア(2024年) | 主な理由 |
|---|---|---|
| ノルウェー | 約89% | 再生可能エネルギー豊富、水力発電中心 |
| 中国 | 約25% | 大気汚染対策、自国産業育成、補助金 |
| 欧州全体 | 約15.4% | ディーゼル車への反発、パリ協定 |
| アメリカ | 8.1% | 政策支援(バイデン政権)、テスラの成長 |
| 日本 | EVは少数派(ハイブリッド6割) | エネルギー事情、自動車産業保護 |
日本
日本では、プリウスをはじめとしたハイブリッド車が主流で、2024年時点で新車販売の6割以上がハイブリッドとなっています。
EVに対しては、充電インフラの未整備や電源構成の問題(火力発電依存)から懐疑的な意見も根強く、急速なEVシフトは進んでいません。
アメリカ
アメリカでは、オバマ政権下で「グリーン・ニューディール」が掲げられ、EVや再生可能エネルギーの導入が強く推進されました。
テスラ社の躍進もあり、EV産業は拡大を見せていますが、それでも2024年のEV新車比率は8.1%とまだ一桁台にとどまります。
ヨーロッパ
ヨーロッパでは、ノルウェーが水力発電による再生可能エネルギー比率の高さからEV化が最も進んでおり、2024年時点で新車の約89%がEVです。
また、ディーゼルゲート事件以降、ディーゼル車の信頼性が大きく損なわれたこともEVシフトの要因となりました。
中国
中国では、都市部の深刻な大気汚染やエネルギー安全保障の観点からEV推進が国家戦略として進められ、巨額の補助金やナンバープレート規制などが制度化されました。
その結果、2024年のEV販売台数は771万台に達し、世界最大のEV市場となっています。
現実に直面しつつも進化するEV
EVには当然ながら課題もあります。
代表的なものに、航続距離の短さ(特に軽EVで顕著)、冬場のバッテリー性能低下、充電設備の不足、そして車両価格の高さが挙げられます。
都市部では急速充電設備が整いつつあるものの、地方では未だ数が少なく、特に集合住宅では自宅充電が困難なケースが多く見られます。
また、バッテリーの経年劣化による再販価値の低下や火災リスクなど、安全性への不安も指摘されています。
さらに、EVが環境に優しいという前提についても議論があります。
走行時にCO2を排出しない一方で、製造時に多くのCO2を排出し、かつ電力源が火力発電に依存している場合、トータルでの環境負荷は必ずしも低いとは言い切れません。
結論:EVは未来につながるのは間違いないが、現状では過渡期
EVが推される理由は、「環境問題」「国家戦略」「技術革新」など複雑に絡み合ったものです。しかし、それが消費者の「使いやすさ」「経済性」と噛み合っていないのも事実。
しかし現時点では、価格、インフラ、性能、安全性など、越えるべきハードルが多く残されています。
今後、全固体電池などの次世代技術や、再生可能エネルギーの普及、補助制度の持続的整備が進むことで、より現実的かつ持続可能なEV社会が実現されることが期待されます。
そのためにも、消費者・メーカー・政府が連携し、「本当に求められるEVとは何か」を問い続けていく必要があるでしょう。

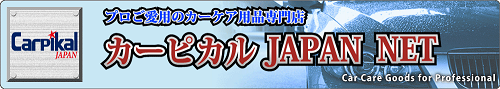

コメント